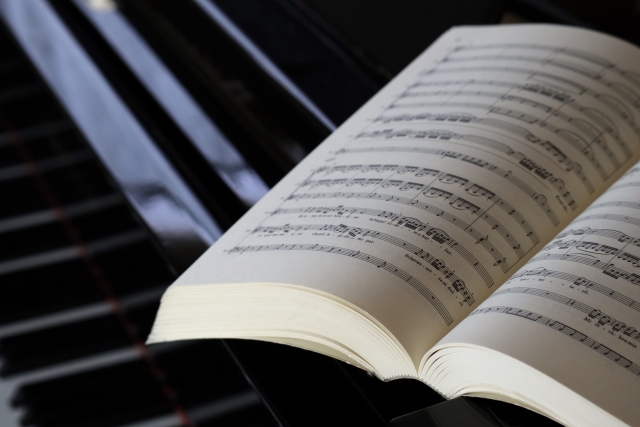こちらのページでは、管理人の考えるベルカント唱法のやり方、歌い方を解説しています。
ベルカント唱法を独学で学びたい方、勉強中だけどうまくいかずに迷っているという方へのヒントになれば幸いです。
※当ページは随時更新中です。
当ページの内容は管理人の経験に基づく個人的主観・感覚によって書いております。この内容をもとに実践され万が一、何らかの不都合や損害が発生したとしても、当サイト及び管理人では責任を負いかねますのでご了承ください。
当サイトをご覧になった方からの発声法や音楽のレッスンのご要望は受け付けておりません。
【はじめに】管理人と恩師の情報
プロフィールでも書きましたが、管理人の歌スペックをもう一度軽くご紹介しておきます。
某音楽大学の声楽科卒、軽めのコロラトゥーラ系ソプラノ。
イタリア留学などで修業を積みつつ、コンサートに出演するなど音楽活動を行っています。
長く師事していた恩師の影響でベルカント唱法に傾倒し、恩師の教えをもとにより自由に歌うためのベルカント唱法を現在も独自に研究中。
レパートリーはイタリアオペラ中心に、フランスやドイツものの軽めのもの、たまに歌曲などもやっています。
そして、私が非常にお世話になった恩師(女性)はこんな方です。
日本の某音楽大学卒業。
イタリアに渡り、10年もの間イタリアで偉大なるイタリアオペラの黄金時代を知っている音楽家たちに師事し、ベルカント唱法を研究。
複数の国際声楽コンクールでの入賞、イタリア、フランス、日本で多くのコンサートに出演、リサイタルも開催。
その後日本に帰国し、独自で構築したベルカント唱法のメソッドを日本で広めていく活動を始められました。
私はこの先生に出会って、世界が大きく変わりました。
恩師のベルカント唱法メソッドが私を救ってくれた
なんとか音楽大学の声楽科に入れたものの、声は細くて不安定だし、まともに一曲歌いきれないし、つねに歌う時に自分ががんじがらめな、不自由さを感じながら歌っていました。
いつも自分の歌に自信がなくて、上手くなりたくて頑張っているけど、それが毎回裏目に出る。
そんな非音楽的だった私に、わかりやすくベルカントの歌い方を教えてくださったのが恩師です。
恩師のメソッドは日本の中ではかなり独特なアプローチですが、非常に理にかなっています。
このページでは、私が恩師から教わったベルカント唱法のやり方、そして私が恩師の教えをもとに試行錯誤してわかってきた事をもとに書いています。
日本で伝えられている一般的なやり方とはかなり異なる考え方であること、そして管理人の主観と感覚も交えてお伝えしていることを、まずはじめにご了承いただければと思います。
ベルカント唱法とは
「ベルカント唱法とはどんな歌い方か?」というのはさまざまな考え方があり、定義も数多くあります。
なのでここでは細かい事はおいといて、私がざっくりととらえている
- イタリアで生まれた歌唱法
- 人間の持つ声の可能性を最大限に引き出す
- その人の個性を最大限に引き出す
- 不自由さがなく、自由に喋ったり表現しながら歌える
このような、素晴らしい歌い方だということぐらいを知っておいて頂ければ充分かと。
ベルカント唱法は、その人の声が持っている可能性を最大限まで引き出すので、どんな身体でもどんな声の人でも、その人らしさがわかる、魅力的な歌が歌えるようになります。
オペラ界のディーヴァ、マリア・カラスも「悪声」と言われるほどの個性的な声でしたが、ベルカント唱法で歌うことにより、ドラマティックな表現力を溢れさせて今なお多くのオペラファンを魅了しています。
ベルカント唱法のやり方・歌い方の基本編【独学の方にも】
ではここから、ベルカント唱法のやり方・歌い方を解説していきます。
先ほども書きましたが、私の恩師の独自メソッドと弟子の管理人の主観&感覚である事をご了承ください。
こちらでお伝えする内容は、ご自身の声に合った声種を正しく選んでいるという前提で書いております。
もしご自身の声に合っていない声種・レパートリーで歌われている場合、このメソッドの効果は100%発揮できない可能性もあるのでご注意ください。
ご自身の声種が分からないという方は、とりあえず軽い声種(女性→ソプラノ・リリコ・レッジェーロ、男性→テノーレ・レッジェーロ)のレパートリーをやっていれば声を傷める危険性は低くなります。
ちなみに、日本人はその体形・骨格からかなりの割合で女性はソプラノ・リリコ・レッジェーロ、男性はテノーレ・レッジェーロであると言われています。
喋るように歌えばベルカント唱法になる
ベルカント唱法で目指す究極のところは、
喋るように歌う。
これだけ。
これさえできればベルカント唱法マスターです!
「は?それだけ?」と思われるかもしれませんが、冗談ではなく大真面目に言ってます。
声楽の発声法を習う際、「喋るように歌って!」と言われた経験があるかもしれません。
それは「もっと自由に!」「脱力して!」などの別の意味で言われている可能性もあります。
ですが、真のベルカント唱法の究極のところは
喋るのと全く同じように歌う。
これなんです。
「全く同じ」というのが非常に重要なポイント。
100%喋っているのと同じやり方で声を出す【ベルカントの基本三原則】
「喋るみたいに」とか、「喋ってるつもりで」とか、ものの例えではないんです。
100%(むしろ200%の気持ちで)、喋っているのと全く同じように声を出すんです!
「喋っているのと全く同じ」とは、
- その音程で喋る時と同じテンションで
- そのテンションで喋るのと同じ声の位置(ポジション)で
- そのテンションで喋るのと同じ自由なノドで
声を出す、ということを指しています。
この3つのポイントは、私の恩師が提唱しているベルカント唱法メソッドの教えをもとに、私がより噛み砕いてわかりやすくしたもの。
このメソッドでは一番大切で、かつ「これだけ守ってれば他は気にしなくてもいい!」ぐらい大切な、いわばベルカント唱法のセンターピンとも言えるものなので、ここでは「ベルカントの基本三原則」として常に意識しておいてください!
その音程で喋る時と同じテンションで言う!
「その音程で喋る時と同じテンションで声を出す」という事について少し解説します。
「歌を歌う」ということを意識しすぎると、どうしても綺麗な声や大きな声を作ろうとしてしまいがちですが、ベルカント唱法の理想は「喋るのと同じに」ですから、自分が普段出さないような声の出し方をするのはNGです。
「音程で喋る」と書くとわかりにくいかもしれませんが、私たちは普段、かなり広い音域を使って喋っています。
- 気持ちが暗い時は低い声
- 冷静に喋る時は中音域
- 楽しく、ハイテンションで喋っている時は高めの声
- 驚いた時などは悲鳴に近い声
こんな風に、喋るテンションによって使う音域もさまざまです。
偉大なる作曲家は歌い手の声についても精通していますから、表現して欲しいセリフ(歌詞)は「その表現のテンションに合った音程」で書かれています。
例を挙げると、
「彼と結ばれて幸せ!」という歌詞なら、普段のあなたが「彼と結ばれて幸せ!」というテンションでそのセリフを言う、その音程になっているはず。
「私の普段のテンションとは違うんだけど!」という場合は、表現が足りない(俳優になったつもりでセリフを言いましょう!)か、本来のあなたの声種とは違うレパートリーを選んでいる可能性があります。
という訳で、そのテンションで喋る、そのテンションのままで声を出せばいい、という事ですね。
単純に声を出してその音程を言えたとしても、そのテンションで言っていない場合はポジションの位置がイマイチなので歌うのに不自由になるはず。
なので、そのテンションのままでセリフ(歌詞)を喋る、という事は非常に重要なんです!
ベルカント唱法のやり方・歌い方の訓練編【歌う筋肉を育てよう】
ここでおさらいしておきましょう。
ベルカント唱法で一番重要なのは「喋っているのと全く同じように声を出す」ということでしたね。
「喋っているのと全く同じように」というのは、
- その音程で喋る時と同じテンションで
- そのテンションで喋るのと同じ声の位置(ポジション)で
- そのテンションで喋るのと同じ自由なノドで
声を出す、ということでした(ベルカントの基本三原則)。
ベルカント唱法のやり方には歌う筋肉が必要
こうして文章で見るとシンプルに感じますが、実際にこの3つのポイントを意識して声を出そうとすると、最初は
「この状態から歌うなんてできない!」
と思うかもしれません。
その状態で歌声を出そうとしても、出ない感じに思えてしまうんですよね。
いくら「喋るのと100%同じように」と言われても、ただ喋るだけと歌うのはもちろん違う行為です。
ですから、100%喋るのと同じ身体の状態では歌うことはできません。
身体まで100%同じにしていたら、ただ喋るだけになってしまいますからね。
身体の筋肉を育てて支えを作る
ここで出番となるのが身体の筋肉。
体を支えて声だけを自由に出せるようにするために、背中、お腹、腰、お尻、脚の筋肉に頑張ってもらうのです(ノド周辺や顔の筋肉は頑張る必要はなく、自由に)。
頑張ってもらうと言っても、そこに力を入れてわざと頑張らせるのではなく、喋るのと全く同じテンション・ポジション・ノドの状態で歌う感覚をまずは最優先します。
そうやって喋るのと同じように声を出そうとすることで、自然と身体の筋肉が頑張ってくれるようになります。
最初のうちはその筋肉が育っていないので、「喋るのと全く同じじゃ歌えない!」と思うかもしれませんが、喋るのと全く同じテンション・ポジション・ノドの状態だけで言う事を最優先して声を出し続けていれば、その筋肉はだんだん育ってきます。
なのでとにかく、喋るのと全く同じテンション・ポジション・ノドの状態の喋り方で声を出すことを常に最優先していくことが、ベルカント唱法を歌える身体を育てる近道なんです。
(「声を出す」という書き方をしていますが、「そのテンションで言う」という感覚の方が近いです。「歌う」という感覚にとらわれすぎていると言いづらくなります。)
ベルカント唱法に必要な体を根気よく育てる
ここまでに書いたことをやろうとすると、最初のうちはまともに歌えないし、音程もとれなくなるかもしれません。
いったん歌い方がリセットされた訳ですから、歌がヘタになった感覚におちいると思いますが、自由に歌うための筋肉を育てている最中なので気にせず「普段のあなた」のままで喋り続けてください。
根気強く自分の普段の喋り方(喋るのと全く同じテンション・ポジション・ノドの状態)を常に最優先し続けることで、ベルカント唱法が使える身体が徐々にできあがってきます。
ベルカント唱法のやり方を上達させるために避けるべきなのは、喋るのと全く同じテンション・ポジション・ノドの状態では歌えないからと言って、違う声を作ってとりあえず歌ってしまうこと。
そうすると一見声は出ますし音程も作れますが、支えとなる筋肉がなく、ノドまわりの部分に負担をかけることになりますから、ノドに良くないし歌うのも不自由だし、悪い歌いグセがついてしまいます。
なのでできる限り、喋るのと全く同じテンション・ポジション・ノドの状態で言うことを心がけましょう。
「人前で歌うからヘタに思われたくない」「または音程が作れなくてヘタな感じが辛い」というのであれば、筋肉が育っていなくても歌える、使われている音域の狭い曲を選ぶといいかもしれません。
【Q&A】ベルカント唱法のやり方、こんな時どうする?
この章では私が恩師から教わったメソッドでベルカント唱法を追求していく際に、ぶちあたりがちな壁、想定される疑問・混乱するケースを挙げ、それらの対処法や考え方について回答していきます。
注意して頂きたいのは、あくまでも「私が恩師から教わったベルカント唱法のメソッドでやっていく場合」に想定される疑問や混乱に対する、「私の恩師の回答と、恩師から教えを受けた私がベストだと解釈している回答」だということ。
他のメソッドでやられている場合はこれらの疑問や混乱は出てこないかもしれませんし、対処法や考え方がまるっきり的外れに感じられる可能性もありますから、人によっては全く使えないQ&Aであることをまずご理解頂ければと思います。
では、思いつくまま挙げていきます!
管理人がベルカント唱法のやり方に気づくまでの道のり
わたくし管理人も、まだまだ修行中ですが、いちおう「ベルカント唱法ってこんな感じかも」とうっすら感じるところまでは来ています。
それ以前は自分なりに頑張っていたつもりでしたが、やってもやっても全然うまくいかず、逆に不自由になり、歌っている最中は常にがんじがらめになっているような歌い方をしていました。
それが、先ほどからお伝えしている恩師のメソッドである「喋っているのとまったく同じように声を出す」という事だけを追求し、
- その音程で喋る時と同じテンションで
- そのテンションで喋るのと同じ声の位置(ポジション)で
- そのテンション喋るのと同じ自由なノドで
という事を心がけていたら、だんだんとベルカント唱法らしい、自由度が高い歌い方ができるようになってきました。
ここでは独学中の方や、ベルカント唱法のやり方について悩んでいる方の参考に少しでもなるように、わたくし管理人のこれまでやってきた歌い方の遍歴をご紹介していきたいと思います。
小学生・中学生時代:100%ノドで押していた
私が歌を始めたのは小学生の頃。
合唱に力を入れていた担任の先生が大好きで、その先生に褒められたい一心で大きな声を出そうとノドで押しまくって歌っていました。
中学に上がってからも合唱を続けたくて合唱部に入部。
そこでも完全にノドまかせで、どれだけ大きな声を出せるかが重要でした。
高校時代:ノドで押しながら声楽をするのに混乱
歌で音大に行こうと決め、声楽のレッスンをスタート。
メゾソプラノの先生についたものの、ノドで押す習慣から脱却できず、先生もどうすればいいかわからなかったようで、問題児扱いされてました。
それでもレッスンを続け、なんとか音大に入学できました。
音大時代:得意な音域だけでごまかしていた
音大に入ってからも結局ノドで押すやり方は変えられず。
ついた先生はバリトンだったため、高めの私の声の扱いに困っていたようでした。
もともと高めなので上の方が出しやすく、五線内では声がひっくり返りまくっていました。
声を出そうとしてもすぐにまともな声は出ないし、音程はフラフラするし、息はすぐなくなるしで、いつ変な声が出るか、綱渡り状態で歌っていました。
声が変になってしまうのが怖くて、常に声を前に出そうと押しまくってましたね。
(今思えば、押していたから変な声だったのに…)
なので一曲を歌い切るために、比較的安定する音域の、できるだけ高めの音域の曲ばかり選んでいました。
先生も高いソプラノの曲はあまり知らないので、かなり放任で勝手に歌っていました。
音大卒業後:「ノドで押していた」ことを自覚する
音大を卒業した後、演奏家になる度胸もスキルもなかった私は、普通に働き始めました。
ですが、下手なりに歌うことは好きだったため、大学時代の先輩が紹介してくれた、良さそうな先生のところに通い始めました。
その先生はソプラノで軽い声なので、私とほぼ同じレパートリー。
学生時代は歌わせてもらえなかった高い音域のアリアなどもどんどんやらせてくれて、自分の声の可能性が広がっていくようで、すごく楽しかったです。
ですが、この頃もまだまだノドで押していました。
その先生もベルカント唱法を研究している方だったため、自由に歌うためのヒントをたくさん下さいました。
この先生についてはじめて、自分がいかにノドで押していたか、と自覚することができました。
とはいえ、自覚してもすぐには直らず…。
基本的な体の使い方や考え方を教えて頂きながら、レパートリーを増やしていきました。
恩師との出会い:私の歌人生を変えるベルカント唱法メソッドに触れる
その後いろいろあり、先ほどからご紹介しているベルカント唱法の独自メソッドを確立した恩師の先生(女性)につくことになりました。
恩師には数えきれないぐらい沢山のことを教えて頂きましたが、「どうやったらいい声を出せるか」という考えで頭が凝り固まっていた私は、まだまだノドで押していました。
「声を作るにはノドをコントロールしなければいけない」という考えに支配されていたんです。
(もちろん、声を出すには声帯をきちんと使う必要があります。ですが、声帯を自分でコントロールしようとすると、不自然になってしまいがちなので注意が必要です)
そんな、不自然なことばかりして悩んでいた私に、恩師は繰り返し言ってくれました。
「声を作るんじゃない。まず音楽を作って。」
「いい声で歌おうとしないで。どういう風に言うかが大事だから。」
「どういう音楽かを先に考えて。声はそれについてくるから。」
今思えば、本当にこの通りで、人に教えるにはこういう風に言うしかない事も分かるのですが、当時の私はこれが全然わかっていませんでした。
「それはいい声を出せる先生だから、そういう風に思うんだ。まずいい声を作らないといい音楽だって作れない。」
そう思っていたんです。
ですが、それは完全に間違っていました。
恩師が繰り返し言ってくれた言葉が、真実だったんです。
恩師の言葉はこれ以上ないくらい歌の本質をとらえていて、わかりやすい言葉だったと今ならわかります。
演奏家として活動開始:不自由さに苦しめられる
しばらくのあいだ恩師のレッスンに通っていた私は、粘り強い恩師のおかげで亀の歩みのように少しずつできる事が増えていきました。
恩師のすすめもあり、いくつかのオーディションやコンクールに挑戦し、入賞などの結果を残しつつ、コンサートに出演できるようになりました。
ですが「自分で声を作らないとダメ」という考えに支配されていた私は、そうなっても歌っているときの不自由さに苦しめられていました。
相変わらず中低音域はものすごく苦手で、声がひっくり返ることもしょっちゅう。
本番で歌っている間は常に「無事に歌いきれますように」と祈り、冷や汗をかきながら歌っていました。
そんな私も恩師のレッスンの時には理想に近い声が出せることもありました。
今思えば恩師は色んな手を使って、歌う時のポジションを最良のところにはめてくれていたんだと思います。
だからこそ、恩師のレッスンの時と自分一人で歌っている時の差が激しく、「先生がいないとダメだ」という気持ちが強くなっていきました。
ちなみに、イタリアに留学したのもこの時期。
恩師から離れるとノドで押して歌っていた私は、本場イタリアの学校で教わっても、全然上達しませんでした。
イタリアで教えてくれた先生たちも、どうすればいいか困っていたようです。
そう考えると、恩師がどれだけすごいかがわかります…。
一人で修業開始:まずポジション探しから
長いあいだ恩師にお世話になりましたが、色々あり独り立ちすることに。
恩師に教わったことを無駄にしないためにも、一人である程度歌えるようになりたいと修行をスタートさせました。
とはいえ一人になって最初の2年ぐらいは、一人でやる勝手がわからず、昔のノドで押す歌いグセばかりが出て、何度も挫折しそうになりました。
恩師に教わったことを忠実に実行していたつもりが、一番大事な部分である「喋るのと全く同じように」ということが中途半端で、できていなかったんです。
この基本中の基本ができていなければ、他の教えを再現しようとしてもできないのは当然。
恩師に教わっていた時の雰囲気だけを再現しようとしていた私は、相変わらず不自由に、がんじがらめな歌い方をして一人で苦しんでいました。
ですが「一人では何もできない」と思いたくなかった私は、何度も恩師の教えを思い出し、その言葉通りに忠実にやることをひたすら繰り返しました。
「そのテンションで喋るのと全く同じように」ということが特にできていないと自分で感じていたので、その音程のテンションで喋るのと全く同じポジションで歌い始める、ということを特にこころがけました。
この頃はとにかく、喋る感覚と歌う感覚を近づけるために、その音程でまず喋ってから、同じポジションとやり方で歌う、という事を繰り返していました。
苦しみの中で光を見つける:自由さがわかってくる
一人で恩師のやり方を繰り返しながら3年が経過。
恩師の言葉を思い出し、フレーズごとにその言葉に忠実にやっていく。
そんな練習をしていたら、じわじわと恩師とやっていた頃の感覚が戻ってきました。
それでもまだまだ不自由さを感じまくっていた私。
あるコンサートに出演するために、久しぶりに大きなアリアを練習していましたが、不自由な状態では歌いきれず、不安と焦りの中で練習を続けていました。
上手くいかない時に毎回必ず思い出すのは恩師の言葉。
「そのテンションで言う言い方だけで、あとは何もしなくていいの。」
「そのテンションで言うのと同じぐらい、簡単に歌えるものよ。」
特に不自由さを感じていたこの頃に思い出していたのはこれらの言葉でした。
「言うのと同じように簡単に歌えるなんて、そんなことあり得ないでしょ!」
少し前の私だったら、そう思っていたでしょう。
ですが、本番も近くなり崖っぷちに立たされた私は、恩師の言葉にすがるしかありませんでした。
先生の言葉は常に本当だった。
だから、今回も先生の言葉通りに忠実にやってみよう。
そう思い、とにかく「簡単に歌う」ことを意識して練習を続けました。
Youtubeなどで大歌手が歌う姿を見ていると、皆いとも簡単そうに歌っていますよね。
そういう姿を日々見ていたこともあって、恩師の言葉に説得力を感じるようになっていました。
この時は「何としても本番を成功させたい」という気持ちから、恩師の言葉だけを頼りに、「簡単に、喋るのと同じようにやる」という事をひたすら毎日身体に染みこませるようにしました。
すると、他に策がない崖っぷちの状態だったからこそ、強制的に恩師の言葉を受け入れるしかなく、じょじょに恩師のメソッドの理想の歌い方に近づいてきたんです。
つまり、だんだんと不自由さが減って、思った通りに歌えるようになってきたのです(あくまで当社比です)。
この時の本番前の時期は、大げさに言えば「覚醒」したような感覚がありました。
本番前に自由な歌い方に覚醒した時の記録(2021年1月~3月頃の備忘録)
参考になるかわかりませんが、この時期の思考や感覚の移り変わりを記録として残しておきます。
そのテンションで言う位置(ポジション)で、もっと簡単に、喋るのと同じままに歌いたい
↓
曲の後半になるとノドが固まってきて苦しい、だから喋る時と同じ自由なノドでやりたい
↓
ノドが固まったままだと続けて歌えなくなるから、フレーズごとにノドを脱力させよう
↓
フレーズ終わりごとにノドを脱力(+フレーズ始まりにまた固める)させていたら何とか続けて歌えるようになったけど、いちいち脱力するアクションがなんか変…もっと普通に歌いたい
↓
脱力することばかりを意識していたら、そのテンションで言うポジションが崩れてきたので、ポジションは言うままの位置で死守しなおす
↓
言うままのポジションを死守したままで、フレーズの合間にノドを脱力させながらやり続けていたら、「そもそもノドが脱力したままでもフレーズが言えるのでは?」いう感覚になってきた
↓
その音程のテンションで言うポジションで言うのは崩さない(=背中や腰などはポジション維持のために勝手に動いてくれる)で、ノドだけを普通に喋るのと同じように自由に脱力させて言うだけでいい
↓
ポジションが自由に言えるところを保っていて、ノドも自由に言えるから楽に歌い続けられる!
…という感じです。
個人的な感覚で参考になるか分かりませんが、「ノドでコントロールする」「ノドで声を作る」という感覚で上手くいかない方にはもしかしたらヒントになるかもしれません。
こうして書き出してみると、歌う時にノドを固めている(声帯ではなく声帯周辺に力が入っている状態)のがダメだったと一発で分かるのですが、当時は「これが歌う感覚・ノドを使っている感覚だ」と思い込んでいたんですよね…。
途中で「フレーズ終わりにいったんノドを脱力して休ませればいいのでは?」と思いついたのは良かったですが、そこからまたご丁寧にフレーズ言い始めでノドを固め直していたのが笑えます。
「ノドを使って歌う」という感覚を思いっきり間違えていたんですね。
で、フレーズごとのノドの脱力をこまめに練習していたら、フレーズの歌いだしに間に合わずに脱力したままのノドでフレーズを歌ったことがあったんです。
その時に「ん?なんかノドが自由なままで言えた気がしたぞ?」と一瞬感じたのですが、途中ポジションの維持ができていなかったので、その感覚はその時一回だけで終わりました。
その後、ポジションが崩れてきた感覚があったので、ポジションを死守しなおすことに。
そのポジションで脱力しつつ言っていたら、なんだか少し自由な感じになってきました。
そんな事を繰り返していたら、「は!このポジションならノドは常に脱力でも言えるんじゃない?」とはたと気づき、やってみたらビンゴ!
この時本番3日前。よく間に合った私!
おかげ様で本番はかなり良い出来(当社比)になり、久しぶりに楽しく、自由な感覚で歌うことができました。
その後も別の曲でこのやり方を試していますが、ちゃんとこのやり方で忠実にやれば歌いにくさは感じません。
背中や腰などの身体にはしっかり働いてもらうことになりますが、自分の言いたいこと、やりたい音楽をちゃんと表現できます。
この時の感覚や思考がこれだけ移り変わり、ある程度自由な感覚まで持ってこれたのは、
恩師のベルカント唱法のメソッドを信じて、そのやり方でできるように何度も繰り返したことで、必要な体の筋肉が育った
というのも大きかったと思っています。
そして、いまだに「絶対に心がけねば!」と思っているのは、やはり
その音程のテンションで喋るのと全く同じポジションで言う
という事。
いくらノドを自由にしても、身体が育っても、ポジションが少しでもブレていたら自由には歌えません。
なので、
どういう風にそれを言いたいか
をしっかりと自分の中に持って、
そのままそれを言う
というシンプルなことをこれからも追及していきたいと思います。
そうすれば、今よりもっともっと自由に、もっともっと楽しく歌えるはずですから。
歌おうとして邪魔さえしなければ本当に喋るままで言えることを実感してきた(2021年4月~2022年8月までの移り変わり)
この記事をしばらく更新できず、久しぶりに追記します。
この前の部分が確か2021年3月ごろの話で終わっていたので、その後も訓練を続けていた私が、さらに良い方に変化していった感覚の移り変わりについて、また備忘録として残しておこうと思います。
その後もひたすら、
言いたい言い方そのままで、
言いたい言い方のポジションで、
言いたい言い方の言い方で、
言いたい言い方のその声で、
全てを言い続けられるように、
ひたすら身体にその感覚を叩き込みました。
どの音程も、どんな音型も、その音程のテンションで言いたい言い方、言いたい言い方のノドでやるだけ、ということを続けていました。
言葉にするとシンプルですが、それまでの私は「言いたい言い方」ではなく、「キレイそうに聴こえる声」を作ることに必死になっていたので、自分の本来の喋り方ではなく、自分が自由になる声や言い方を完全に潰しながら歌っていました(今思えば歌っていたのではなく、ノドと身体を締め付けて苦し気な声を出していただけ)。
なので、自分が普通にそのテンションで喋る言い方で歌った経験がなく、隙あらば声を作ろうとこれまでの習慣が邪魔してきます。
その音程で普通に喋る声をまず出してみてから(セリフを言う感じで)、それと同じ状態を保って歌い始めるという練習を続けていたのですが、最初の1音はそのまま言えるようになっても、2音目からは声を作ろうとしてノドで押したり固めたりしてしまいます。
最初のうちは自分が2音目から固めているという事にすら気づかず、「最初はいいのに後半歌いにくいな」「続けて歌えないな、なんでだろう?」と疑問に思っていました。
恐るべし、これまでに積み上げてきたノドで押しまくる習慣の強さよ(笑)。
それでもひたすら、「その音程のテンションで、人に伝える、人に喋るのと同じように言う!」ということを基準にして、自分の歌がその基準に近づくように、1フレーズごとに、1音ごとに繰り返して身体に叩き込んでいきました。
まだ歌う用の声を別に作ろうとしていた
この時、なんとなくやっている方向性は悪くないと自分では思っていましたが、追記しているいま(2022年8月)振り返ってみると、
「喋るのと同じ言い方の声を作ろうとしていたなぁ」と思いますね。
その後、「本当に喋る声そのもので音程を言えば自由に歌える」ことがわかってくるのですが、この頃はまだ、
「喋るのと同じ言い方で声を作ればいい」と思っていて、「喋る声そのもので言うだけ」というところにまでは思い至っていなかったですね。
まだ、歌う用の声を作ろうとしていた、と言いますか…。
でも、その歌う用の声を作るという考えがあると、自由には歌えないんです。
だって、自由に喋れる時って声を作らないじゃないですか。
逆にいい声で喋ろうとすると、不自然な力が入るから自由に喋れないですよね。
だから歌う用の声を(わざわざ)作る、というのが、逆に歌いづらくなる原因となっていたんです。
その後、訓練を続けていくうちに、
「ただ脱力するだけでなく、喋る状態と全てを同じにする」
という事も必要だとわかってきました。
1音ごと、フレーズごとに喋ってみて(または喋るイメージをして)から、それに近づくように歌っていたので、だんだんと「あれ?歌う時に全然別のことしてるぞ?」ということに気づいてきたんですね。
この頃気をつけていたことは、具体的に言うと
- 喋る時と厳密に同じポジション
- 喋る時と厳密に同じ言い方
- 喋る時と厳密に同じ上向き加減
- 喋る時と厳密に同じ口の使い方
- 喋る時と厳密に同じノドの自由さ
- 喋る時と厳密に同じ身体の使い方
- 喋る時と厳密に同じ音から音への移動の仕方
あたりですね。
とにかく、すべて!を喋る時と同じ状態にすることをひたすら心がけて繰り返していました。
地に足のついた「地球の言い方」で言う
そしてこの後に、私独自の
「地球の言い方で言う」
という考え方が生まれました。
これはどういう考え方かというと、
「私が普段いろんな感情をこめて話している言い方のまま、その地に足のついた言い方のままで言う(歌う)」
というもの。
ふとした時に、私はそれまであまりにも声を作ろうとしすぎていたことに気づいたんです。
自分の声のままでやるのが一番いいのに、「良い声」を作ろうと必死になっていたあまり、自分とはまったくかけ離れた、「別の惑星」で声を出そうとしていたと。
別の惑星レベルで声を作ろうとしていたら、そりゃあ手に届かなさすぎて、自由に歌えないに決まっていますよ。
だから、普段私が使っている、自由に人に伝えたり叫んだりして、普通に喋れるその声のままで言う(歌う)、それが一番だということで、「地球の言い方で言おう」という風に考えが切り替わりました。
わざわざ良い声を作ろうとすることが、逆に良くない声になってしまう
普段の自分の声で、喋っているのが一番自由で一番楽ですよね。
でもなぜか、良い声を出すことにとらわれてしまうと、「自分の普段の声じゃいけない」と思ってしまう。
だから、良い声を作ろうとして別の惑星の、わざわざ出しにくい声、出しにくいやり方で言おうとしてしまうんですよね。
でも、素敵に歌っている歌手の皆さんは「自分の声(地球の言い方)」で歌っています。
自分の声100%そのものだから、自由に、美しく歌えているんです。
そんな美しい歌手の歌を聴いて、「私もああいう声を出したい!」「キレイな声を出したいから声を作る訓練をしよう!」と誤解して、自分の声とは違う作った声を出す方向に行ってしまうと、逆に良い声じゃなくなるし、歌いにくくなります。
(「ああいう声を出したい!」という願望は悪くはないですが、声は1人1人違うのでモノマネをすることも自分とは違う声を作って不自由になる原因となってしまいます)
「私も自分の声で歌おうとしているのに、なぜ上手く歌えないの?」という方は、自分の声に100%なっていないから。
何かしら歌おうとしている要素がまだあるので、不自由に感じるし、自分の自然な声のままでやれていないので、中途半端な状態なんです。
その中途半端状態から抜け出して「自分の良い声」で歌うためには、ひたすら普通に喋る声(地球の言い方)で言えるように、その状態に近づけていけるよう、「普通に喋る→それと同じ言い方で歌う」を繰り返し、その感覚を頭と身体に覚えこませるしかありません。
(普通に喋るとは、その音程のテンションで喋る、という意味です)
地球の言い方さえできてれば、自由に歌うベースはできる
私も地球の言い方という考え方に行きついてからは、これを習慣づけられるようにひたすら反復練習していました。
そうしたら、
全てを地球の言い方のポジションと言い方で厳密にやっていれば、言いたいように自由に歌える
という事がわかってきたんです。
つまり、地球の言い方のままでさえやってれば、ベースはバッチリということ。
なので地球の言い方を最優先して、それ以外の言い方や邪魔してくる感覚は徹底して無視。
他の言い方をしたくなっても採用せずに、どんなに変な声でも地球の言い方に近づけるよう、繰り返しやっていました。
これを続けていれば地球の言い方で言える筋肉が育ってくるので、言えなかった音もだんだんと言えるようになってきます。
そうして練習を続けていたら、また一段、喋るのと同じポジションに近いところで言えるようになってきました。
喋るまま口から出せそうな感覚になってきた
そして、「普通にその音程で喋ってみる(またはそのイメージをする)→それと同じポジションと言い方で歌ってみる」を、1音ごと、1フレーズごとにしつこく繰り返した結果、「これって喋るまま口から出せるんじゃない?」という感覚になってきたんです。
(それまでは作った声で歌う感覚が抜けなくて、喋るのと歌うのは別でしょ、っていう感覚が強くあった)
そして、喋る言い方そのままで口から出せば、余計な邪魔が入らない(普段喋っているのと同じ一番楽な言い方だから)ので、
- 一番楽に歌えるし、
- 一番省エネで歌えるし、
- 一番手っ取り早い(ポジションとか毎回気にしなくていい)
という事にようやく気づきました。
それまでの私は、ちょっと長いフレーズとかちょっと動きがあるフレーズを歌う時には毎回全身の筋肉総動員!って感じで、身体と顔(笑)と声帯を振り絞って歌っていました。
なので練習後は毎回かなり消耗していたし、背中や腰の筋肉が固まってバキバキだったんです。
何曲も続けて歌えて、軽々と歌っている人を見て「なんでそんなに楽に歌えるの?」って思ってました。
今思えば、不自然に声を作ろうとしていたせいで声帯やその周辺にブレーキがかかっていたにもかかわらず、そのまま声を出そうとしていたから他の余分な筋肉まで総動員させないといけない状態だったのかなと。
普段テンション高く喋り続けた後って、多少疲れは感じるけど身体はバキバキにはならないですよね。
だから、声を作ろうとして余計なことばかりしていたから、必要以上に疲れる状態で歌い続けていた訳です。
追記をしているいま(2022年8月現在)では、作った声の割合は減っているので、歌った後の消耗度合いも減ったし、身体のバキバキ感はかなりなくなりました!
昔は歌った後身体がバキバキで筋肉をゴリゴリほぐさないと痛くて次の日歌えないぐらいでしたが、それが「身体を使って歌った!」という風に思っていました。
ものすごい勘違いでしたね…(汗)。
いまでは歌った後はもちろん疲労感はありますが、心地よい疲れという感じです。
背中や首周りの筋肉を使った感覚はあるので、そのあたりを軽く伸ばすぐらいはしますが、固まっている感覚はないですね。
だいぶ身体への負担も減ってきている実感があります。
喋るままの言い方を意識していたら気づいたこと
その後、ひたすら頭と身体に「喋るままの言い方でやる!」という事を覚えこませ、習慣化させる作業を続けていったら、いろいろなことに気づいてきました。
その頃に考えていた頃、気づいたことを以下にまとめてみます。
いい声をつくるために、当てはめる枠(良い声の型)はいらない。普段の自分がそのテンションでお話しを伝えるその言い方、そのままの喋り方、そのままの声でいい。
いい声を作って歌うのではなく、自分の普段の声が一番無理のないいい声だから、そのままで言うだけがベスト。
自分が勝手に作った「良い声の型」にいかに上手く息や声を通すかばかり考えていたが、そうではなくて型はいらない。
自分が普段喋ってる声のまま、本気の言い方(大声ということではなく、本当に普段、そのテンションで喋ってる臨場感ある声のまま言うだけ。
型はいらない。
型を作ろうとするから苦しくなって、歌うのが不自由になる。
歌う時に「歌う前提の喋る声(歌いやすそうな喋る声)」を作りがちだがそれは結局ノドでおしてるので不自由さが残る。
「いくらなんでもこの声じゃ歌えないでしょ!」ってくらい、普段の喋り方のままの声を基準にして、そのまま言う!
歌いにくさ、不自由さがあるのは自分で自分のノドを固めたり押したりして不自由にしているから。それ以外に理由はない。なので一番楽に自由に喋れる普段の喋り方のままやる。
自分の声や普段の喋り方とは違う、良い声を作って歌おうとすることは、ブレーキ(声を作っている状態)をかけながらアクセルを開けて車を前に進まそうとしているようなものなので、声は出しにくくなるし、体も喉も余計な力を入れないと声が出ないので、体もノドも余計疲れて歌えなくなる。
普通に喋っていて自然と身体に力が入る、身体が働いてくれるのはOK。でも意識して身体を働かせようとするのはNG。
歌い出しは上手く行っても、その後や上に上がる時に、がそのままの喋り声では言い続けられない、とノドでカバーしてしまいたくなるが、そこをそのまま我慢して、喋り声のままの状態で言い続ければ、身体が勝手に働いて支えてくれる。
あと、アゴとか上顎とか、唇とか、口の周りとかに、そのテンションで言う以上に力が入ってるのもNG。それだと押してる。
その場合はそこの力を緩めてみるのもアリ。そのテンションで言うのと同じ顔、口の状態でできる。
子音が言えないのは押してるのが原因。
子音は強引に口を動かして言う必要はなく、普通に喋ってるときと同じに言えば、普通に喋ってる時と同じように言える。子音を立てたい時は、立てた喋り方のままで言う。
なんか重複している部分も多いですが、いろいろ思うところがあった時期でした。
歌おうとするブレーキはいらない。喋る声のままで音程を言うだけ。
そして追記をしている2022年8月現在。
本番があり、そこに向けてひたすら喋る言い方のまま歌う練習を続けていました。
その中でさらに気づいたのは、
歌おうとする(声を作る)ブレーキはいらない。言いたい言い方のまま、ノドと身体は自由に、簡単に歌わせる。
その音程のテンションで、人にちゃんと伝えるまま言うのが、一番カンタンで一番楽で一番自由。
そのテンションで本気で喋る、伝える言い方500%のままやる!
本当に本当に言うままで、その通りにできる。
それで言えば、身体が自動的にやってくれる!
言う声で、そのまま「音程を」言うだけ!
ということ。
最後の「言う声でそのまま【音程を】言うだけ!」というのは最近の大きな気づきで、私はそれまで音程はノドで押したり、息を使って音程を移動させて作っていたんですよ(それすらも今まで気づいてなかった)。
だから、最初の1音以外は純粋に喋るままでは全く言えていなかった、息とかノドで押した力で、その勢いにまかせてなんとなくその高さの音っぽいものを言っていただけ。
喋る声のままで言うってことは、喋る声で音程を言うってことですから、ノド周辺の力や息の助けはなく、声帯だけが純粋のその音程の高さを作るってことになります。
例えば、イライラした時に大きめの声で人に「ちょっと!」って呼びかける時。
「ちょ」の音程と「と」の音程は違いますよね(同じ人もいるかもですが…)。
その時、2つの音の間をつなぐために、ノド周辺に力を入れて押したり、息の力で持っていって音程の間を移動させてはいないですよね。
ベースは声帯がはたらいて、「ちょ」と「と」の2つの音を作って発音しています。
ノドや息で押して音程を作っていたことに気づいた
ですが私は、最近になって「ちょ」は喋るまま言えるようになっていましたが、息やノドで押すことが歌う事だと勘違いしてきた期間が長すぎてそのやり方しか知らず、2音目以降の「と」に関しては息やノドで押して音程を作る(持っていく)のが当たり前で自然なことだと思っていたんです(悪習慣って恐ろしい…)。
喋るままで全てを言う練習を続けて、「喋るままで全部言える。もっと楽に簡単に言える」と練習中呪文のように繰り返していたある時、
「あれ?私、喋るままの声で音程ぜんぜん言ってないよね?」
というものすごいことに気づいたのです!
それに気づいたのは本番の数日前。
何とか喋るままで音程が言えるように本番に間に合わせたいと思いましたが、あまりにもノドと息で押す習慣の力が強すぎて、本番では全くそれができませんでした…。
ですが、本番の曲の練習を始めた当初は、さらに息とノドが強かったのでまともに歌えてなかったのですが、ノドや身体のブレーキを外す(喋るまま口から出す)練習を続けた結果、いちおう曲として成立させられました。
練習を始めた当初はどうなることかと思っていて、細かく動く部分は諦めるしかないかとまで考えていましたが、そこも一応は歌えるようになって、自分の中での最低合格点はクリアした感じです。
ですが、「もっと喋るままだけで口からそのまま出して、喋る声のまま音程を言えば、もっと自由に歌えるのに!!」という感覚がものすごく強く残っています。
もっともっと喋るままだけでやれば、今の中途半端な感じから脱出できて、より自由になって
- 自分の声の良さが最大限出せる
- もっとホールすみずみまで響く
- どんなフレーズも軽やかに言える
- 自分の言いたい通りの表現ができる
という状態になれるのではないか、と思っています。
まだ課題はありますが、今回の本番とその前に積み上げてきた練習の中で、
「普通に自分がその音程のテンションで喋るまま口から出せば、それが一番美しく楽に歌える」
ということに気づいて、それに心から納得できたことはすごく大きな成果でした。
本当の本気で、喋るままの声で歌える
少し前までの私は、昔さんざん先生に言われていたにもかかわらず、「喋るままだけで言うなんて、実際は無理でしょ(たとえ話でしょ)」と思っていましたから。
ですが、今はそれがたとえ話ではなく、「そういうつもりで」という話でもなく、本当に「喋るままの声で、その声だけで歌う」という事がベルカント唱法で、それがその人の持つ声の魅力を最大限引き出して、自由な表現ができる、最高の歌い方だと本当に実感しています。
「そんなことない、私はそれができない」と思っている方もいるかもしれません。
ですが、今それができないのは、それをやったことがないから。
自分の声ではない、キレイな声や立派な声になることを一旦捨てて、自分の普段の喋り声のまま厳密にやってみることを、しばらく試してみてください。
おそらく、以前よりは楽に、以前よりは自由に歌えるはずです。
この道を進んでいって本当の意味で喋るままに歌えるようになれば、自分の声の魅力と響きが最大限まで増幅して、かつて自分が憧れていた美しい声や立派な声にいつのまにかなっているはずです。
私もそこに一歩でも近づけるよう、自分の声を大切に、最大限自分の声のままで言う(歌う)ことを、常に意識していこうと思います。
今まで歌おうとして余計なことしかしていなかったことを痛感(2022年9月から2023年3月の移り変わり)
さらに時間が経過し、新しい感覚になってきたので久しぶりに追記します。
とにかく普通に喋るままでできるとわかったので、普通に喋るまま全ての音程を言えるように、余計なところは脱力して、支えに必要な身体の筋肉を育てることを意識して練習を続けました。
(身体の筋肉を育てるイコール、何かを自分でするのではなく普通にただ言うことを優先して身体に自動的に働いてもらう習慣をつけて筋肉を育てる)
ひたすら、ノド、ポジション、空気感などを喋るのと同じに死守しながら歌う(言う)訓練を続けます。
そのうち、
歌う用の歌い方(余計なことしてる歌い方)で歌い始めようとする
↓
喋る感覚と照らし合わせてみると全然違うことに気づく
↓
余計なことをしないように意識する
↓
喋るのと同じように言う(歌い)始める
という一連の流れを続けているうちに、
「あれ?余計なこと(それまでの歌い方)をやめて普通に喋る言い方のままやれば、余計なことをするのとそれを外すのの手間がなくなって、直接喋る言い方でそのまま始められるから、それが一番楽だよね?」
ということに気づき、体感でも実感してきました。
これは恩師に教わっていた頃にも恩師にさんざん言われていたことですが、当時は歌うことイコール余計なことをする(本当に喋るままでは歌えない)と固く信じていました。
ですが不自由の極みな歌い方をしているうちに、さすがに疲れてきて少しずつ脱力して喋る言い方に近づけているうちに、「喋る言い方そのものでやるのが一番いいのでは?」と実感できるようになってきたんですよね。
おそらく若い頃から歌えて、素晴らしいキャリアを築かれてきた方は、喋る声のまま歌うのが当たり前だという感覚が最初から備わっていたのだと思います。
そうしてノドに余計なことはさせず、喋るだけで言う(歌う)のを心がけているうちに、自然と身体が働いてくれるようになるのが分かるようになってきました。
「普通に喋るだけでやる」とさんざんお伝えしてますが、本当に喋るだけだと喋るだけで終わってしまいますよね(笑)。
その喋り声のままで歌うためには歌うための支え(エネルギー)がないといけません。
ノドで押したり支えたりしたら自由に歌うことはできないのでノドに自由に歌わせるためには身体に働いてもらう必要があります。
なので「こんなノドじゃ歌えないよ!」と思うくらい、ノドは支えない、頼りないノド、歌いごたえのない状態のままで言うだけなんです!
そうすれは身体は自動で働いてくれて、ノドには自由に歌わせられるようになります。
それまでは「ノドをちゃんと使う」と言うことと勘違いして、歌いごたえを重視していたので、完全に真逆の方向性にいってましたね…。
(ノドをちゃんと使う、というのは声帯が自由に動けて発音できている状態)
歌おうと頑張ることがむしろ歌いづらくしていた
恩師にかつて、
「あなたたちはどうしてわざわざ難しい方へと、歌いづらい方へと自分から行こうとするの?」
と良く言われてましたが、それは、何をするにもノドに力を入れたり息で押したりして解決させようとしてた(それでしかできないと思ってた)からなんですよね。
当時は恩師の言っていることは3割くらいしかわかってなかったと思います…。
さらに補足すると、かつての私は(今もまだ片鱗が残ってますが)、
歌うためには特別なことをしないといけない
↓
だから喋るままでは言おうとしない
↓
喋るまま言うための筋肉が育たないし使えない
↓
その筋肉が使えないからノドや息に頼るしかない
↓
ノドや息でやると言えないし言いにくい、だからさらに何とかしようとノドや息で色々やろうとする
↓
もっと言いにくくなる…
という悪循環に陥っていました。
それを断ち切るには、喋る声そのままでやろうとすることが必要です。
喋る声100%ですぐには言えなくても、喋る声に近づけようとしていって、余分なものを一つずつ外していけば、その分身体の歌うための筋肉が育っていって良い循環に軌道修正していけるはずです。
さりげなく喋る以上の発音は必要ない
そしてこの間に私が新しく発見したのは、「発音はさりげなく喋るだけでいい」と言うこと。
かつての私は余計なことをしまくっていたために、歌っている時の歌詞の発音を、口まわりに力を入れて押したり、ノドで押したり、息で押したり、とまあ全方向から押しまくって力で持っていって発音していました。
これではせっかく声帯まわりが脱力しててもその先に余計なブレーキがかかっている状態なので不自由なままです。
「脱力、脱力…」ということを心がけているうちにたまに口まわりも脱力できることがあり、その時に声が出しやすく響きやすいと感じたのがきっかけです。
それでそのまま脱力して発音しようと試してみたら、歌の歌詞を言う時の私は、単語ごとに力が入りまくっていて、脱力して言い続けることができなかったんです!
独り言を言う時ってどこにも力が入ってなくてスムーズにボソボソ言い続けることができますよね。
ですが私の場合は歌の歌詞をボソボソ呟き続けることができず、途中でノドがあっちに行ったり、唇に力が入ったり、息で持っていったりしていて、独り言の場所でスムーズに呟き続けることができませんでした。
これをはじめて体感した瞬間、自分がいかに歌う時に普通に喋る以外のことばかりしていたかを思い知らされました。
「普通に喋る」は本当に普通に人に伝える言い方
なので、「ここまでで普通に喋るのと同じように言う」という練習をしていましたが、基準にしていた普通に喋る言い方は本当の普通に喋る言い方ではなく、歌う用に作っていた普通の喋る言い方だったと判明したんです!
私が本来目指していて、おそらく恩師が教えてくれていたのは、普通に人に伝える時の喋り方。
私は歌わないで喋ると言うことは多少できるようになっていましたが、まだまだ、舞台用の作った声での喋り方や、自分一人の枠の中で自分だけに向けたこもった喋り方をしていて、本当に人に伝えたい時の喋り方では歌おうとしていなかったことに気づきました。
そうなると歌う時にポジションも内側に入ってしまうので不自由さが残ります。
ちゃんと、普通に人に伝える喋る方のままやっていれば、ポジションは言いやすいところにいられるので、自由に歌えるようになります。
こう書くと独り言の言い方は良くないように思われるかもしれませんが、独り言を言うときは脱力しているし、自分に聞こえるようにいったん外に向かって伝えているのでOKなんです。
ここから私は独り言で呟く時のノドのようにノドには脱力してもらって、自由に歌ってもらえるように意識をはじめました。
それまでは「ノドや口周りを張って押さないと歌えない(それが押している状態ということにすら気づいていなかった)」と思っていたので、ノドや口に力をいれずさりげなく、ボソボソ呟くだけというノドの使い方にはものすごく違和感がありました。
ですがスムーズに呟き続けられる範囲だけでやっていると、それまでにないほど声がスムーズに出せてなめらかに歌い続けることができます。
それ以前はノドでコントロールしようとして、逆にブレーキをかけていたという訳ですね。
自分のレパートリー内なら高音もそんなに高くない
あと、ノドにブレーキをかける原因がもう一つわかり、それは高音を「高い」と思ってしまうこと。
すでにお伝えしてきたように、自分の声種にあったレパートリーをやっていれば自分の声に合わない高音を出すことはありません。
逆に言えば、自分のレパートリー内であれば、その音域は自分の生活の中で普通に出すことのある声ということ。
にもかかわらず、高めのところを歌う時に「ここは高いから何かしなきゃ」と思ってしまうとそれだけでブレーキがかかります。
高いと思うところも、その音の高さで普通に喋ってみると案外低いもの。
なのでその普通の喋りの範囲内で言う、余計な力の入ってない声帯のままでやると、高めのところも歌いやすくなります。
(もちろんその声帯のまま歌うためには身体に自動的に働いてもらう必要があります。身体に自動で働いてもらうためにはノドや息を使おうとしないことです。ノドや息を作為的に使おうとすると、身体はそっちに任せようとして引っ込んでしまいます。)
身体は楽なやり方を知れば次からは勝手にそっちの方向へ行ってくれる
繰り返しになりますが、「喋るままで言いたいけどそれじゃ言えない(歌えない)」というのは先にノドや息が邪魔してるだけ。
普通に喋るまんまで言えば喋るままで歌えます。
言うのではなく、歌おうとすると余計な邪魔が入り、むしろ歌いづらくなります。
逆にちゃんと普通の喋り方で言えば息の出てくる余地はなくなるので、ちゃんと普通に言えば邪魔ものはいなくなって楽に言えるようになります。
そしてノドは一度外れてしまえば、その脱力感が新しい基準になってそれが当たり前の感覚になるので、次からは一から持っていこうと頑張らなくても以前よりも楽に新しいステージで歌えるようになるんです。
なので普通に喋る言い方だけでやるなら、「これで言える訳ない!」と思えても、まずは身体に任せて身体全体でその言い方を思い切り再現する、という感覚でやってみましょう。
そうすれば身体が勝手にその声で喋れるように働いてくれます。
逆に言えば、普通に喋れる声だけで言い続けるという感覚でもいいかもしれません。
身体を働かせることよりも喋る時の感覚を優先
普通の喋り方のままで身体全体で思い切り言う時に一つ忘れてはいけないのは、喋る時の言い方のバランスです。
身体に働いてもらう感覚がわかってくると、身体で支えさせることにばかり意識がいってしまって、「身体で支えてるからどんな声でも大丈夫」という気持ちになってくることも。
身体が支えていてもノドや息で押すことはできてしまうので、それをしないために、常に普通に人に伝える言い方をし続けることが大切です。
「身体は使っているけどなんだか不自由な感じがする」というのであれば普通に人に伝える言い方のままで言っていないです。
その場合は人に伝える言い方のバランス(上下左右の空間やノドの使い方、発音の明るさなど)をもう一度意識して、そのバランスのままで身体に任せて言うようにしましょう。
しつこいようですが、普通に人に伝える言い方と同じ感覚で喋れるようになることが重要です(身体以外の口やノドまわりでその感覚になるのが特に重要)。
以前はどうやって立派そうな声を出すかしか考えていなかった
この段階で改めて気づいたのは、私はそれまでどういう風に言いたいかを全く考えていなかったということ。
とりあえず声楽っぽく立派にきれいに聞こえそうな声を出すことばかり考えていたんです。
ですが、言いたいことを言いたいように言うノドが一番自由な訳ですから、歌う時も全てを言いたいように言い続ける方が断然楽です!
なので「全ての音で発声に気をつける」ところから、「全てのフレーズで言いたいようにちゃんと言う」方にやり方と考え方をシフトして、それが習慣になるように癖をつけるように今しています。
少し前までは、「丁寧にちゃんと言う」ことを「息を使って押してノドに力を入れて言うこと」だと勘違いしていたんですね。
なので今は「普通に言う言い方で全てをちゃんと言うだけ!」の頭に切り替えている最中です。
今はスムーズに鼻歌で言い続けられる言い方を習慣づけてます
そして現時点では最終的に、
その音程のテンションでスムーズに鼻歌を歌える言い方でちゃんと言う
+
身体に任せて、身体だけで、明るい言い方の鼻歌のバランスで言い続ける
というやり方に落ち着いています。
先程「呟き続けられる言い方」ということをお伝えしましたが、呟くことばかりに熱心になってしまうと明るく喋るバランスがとりにくくなってしまうので、最終的には「鼻歌の感覚でやる方がいい」という結論になりました。
私は長く歌っているとだんだん歌い込みたくなってノドで押しはじめてしまい、後半は不自由になったりノドが固まったりしてしまうのが悩みでしたが、常に鼻歌だけで身体にまかせてやっていれば押しようがないので、長く歌っていてもノドへの負担はかなり減ります。
鼻歌の範囲内で言っていればノドも脱力して自由に動いて音程を作ってくれるので、歌いにくさも減るし、本来の自分の声で歌えるようになります。
なのでいまは「鼻歌の範囲内だけで身体に任せて言う!」ということを死守しています。
ノドや息が邪魔さえしなければ誰でも言いたい言い方のまま歌える
ここまでダラダラと思いついたことを書いてきましたが、改めて今お伝えしたいことを以下にまとめておきます。
本来私たちは全員、自分が言いたい言い方のまま歌うことができます。
それが上手くいかないのは自分で邪魔しているか、ちゃんと言いたい言い方だけで言ってないから。
私のようにガチガチでやってたり、歌うことを「何か特別な声を作ること」と思ってそこから始まった人は、言いたい言い方で言えない邪魔なものが多くなっているので、まずはそれを一つずつ外していく必要があります。
(邪魔なものの例: 前に押す、ノドを過剰に使う、ノドや首やアゴの力、上に無理に上げる力、多すぎる息、息で持って行く力など)
これらの邪魔ものを全て外し終わったら口もノドも自由なので、それで言いたい言い方だけで言えばいいんです。
その言いたい言い方だけで言うために働いてくれるのが身体で、それが自動でできるようになるために筋肉と習慣をつけていくんです。
余計な邪魔ものを外すとその部分が明らかに楽になるので、一度楽になってからまたつけようとすると違和感をものすごく感じるようになります。
なので自然と無理なく歌える方向に身体も感覚も向かっていきます。
邪魔ものを外していくたびに、それなしで何かをしようとするとその代わりの支えが必要になるので、それを身体にやってもらうことになります。
(そこで出てくるのはノドと首と息ではなく!)
いろいろ邪魔ものがついていた頃はそれが邪魔して本来働くべき身体が働いていませんでした。
身体に働いてもらって楽に自由に歌うためには、邪魔ものを一つずつ外して、その代わりに身体に任せていきます。
身体は自分で動かそうとするのではなく、普通に人に伝える喋り方のままで言おうとすれば、少しずつ身体が自然に働くようになってきます。
最初は身体が働く習慣がないため身体が動かない気がするかもしれませんが、身体に任せてその言い方で言っていれば、だんだん身体が働いてくれるようになります。
私ももっともっと自由に、自分の喋り方のままで歌えるように追求していきたいです!
言いたい通りに言えば、それで歌うことができるとようやく分かった(2023年4月から2023年8月の移り変わり)
またまた間が空いてしまいました。
先日本番があり、そのための練習でまた新たな気づきがあったので備忘録的にシェアさせていただきます。
前回は、
- 喋るだけでいい
- さりげなく言う、鼻歌的に言う以上のことはしない
というところの気づきがあって、そこでひと段落しました。
その後、本番に向けて新しい曲(コロラトゥーラ的な歌曲です)を練習していくにつれ、
喋るままでやるだけでいい
というのがさらに進化しました。
こう書くとものすごい事が起こったように思われるかもしれませんが、そんなことはなく、前回の喋るままでいいという気づきが甘かっただけのこと。
「喋るままで、それだけでやればいい!」
という一番大事なことに気づいたのはいいものの、その時点ではわかったつもりでいましたが、実際はぜんぜん喋るだけではできていませんでした。
何ができていなかったかと言うと、やはり昔の思い込みからくる歌い癖で、ノドで支える、口周りを固める、声帯周りを固める、ノドで押す、などをまだまだやっていたんですね。
(でも喋るだけでいい、と最初に気づいた時は「これで外せた!」と思ってた。いま振り返るとこの頃はまだまだガチガチで歌ってたなー、と思うけど、今この文章を書いている状態の歌を1年後に振り返ると「あの時も気づいてたみたいなふりしてるけど、まだまだノドでやってたなー」って思うのではないかと。そしてこれは半永久的に繰り返されるのではないかと予測してます…)
で、その後に練習を続けていくうちに、「あれ?これ喋る言い方と違うよね?」と思う点がいくつも出てきました。
その点が先程お伝えした過去の思い込みからくる歌い癖たちなんですが、その時点でもまだまだノドや口でガチガチでやってたので、
とにかく喋るのと同じに、ノドや口を解放する!喋るのと同じ解放感のままで歌う!
ということをしばらく心がけてやっていました。
それでも過去の歌い癖が出てきてしまい、歌いごたえを求めてしまうので、フレーズの最初だけでなく真ん中や最後まで喋るのと同じ解放感で!を常に意識。
それと同時に喋る以外のことに意識を向けない(ノドで押せそうとかもっと前に行かせたいとか)、喋る以外のことに私は関与しない!という意識もしていました。
ひたすら喋る言い方に近づける作業を繰り返す
そうこうしているうちに、さらに自分はこれまで余計なことしかしていなかったことが浮き彫りになってきました。
普通に喋る時は声帯しか使っていないのに(結果的には他の部分も使ってますが意図的にはと言う意味で)、顔や口や口の中や声帯まわりをものすごく使おうとしていたんです。
これは、良い声で歌おうとして余計なことをしていたからでした。
(そしてそれは逆に響きのない不自由な声になっていた)
なので、
支えは身体だけ!
発音と声帯が主導権を握る!
発音と声帯が全てを支配する!
という意識も加えました。
そうしていると、それまで声帯を動かして(動いていたかはわからないけど)音程を一つずつ作っていたのが、
「あれ?これって声帯が自由なら喋るのと同じライン上で音程の間も滑らかに言えるんじゃない?」
ということがわかり、自由に声帯が動くライン(つまり喋るままの前でノドと声帯が解放されてる場所)に常にいられるように!という感覚に変わっていきました。
邪魔するものが減ってきてだんだん自由に
ここまでで書いたことって結局は、
「普通に言いたい言い方で喋るだけでいい!」
と言うこと。
これはこの文章の最初から一貫して書いていることで、私の恩師がずっと私に言い続けてくれたことでもあります。
普通に喋るまま言う、そのまま歌うだけでいい。
これさえわかればこっちのもん!
あとはただこれを実践するだけ!
と思っていましたが、私の長年の思い込みや歌い癖は悪い意味でコツコツと蓄積されていたのです…。
そしてこの感覚で続けているうちに、口やノドまわりに押す力は必要ない、ということが身体で実感できてきて、
口まわりでしっかり言う!のではなく、口先だけで言うだけでいい、ということも分かってきました。
これは言葉だけ見ると悪いことのように感じるかもしれませんが、それまでの私は口やノドまわりに力を入れて声を押し出そうとしていたので、押すのではなく声帯だけを自由に発音させる、という意味でオーバーぎみにこの感覚でとらえていました。
こういう風に心がけてやっていくうちに、だんだんと声帯の自由度が高くなって、ギリギリ、ギチギチで余裕のない歌い方(声帯が思うように動かない)することが減ってきました。
ひたすら喋るままの感覚を身体に叩き込む
声帯がスムーズに歌える感覚を一度でも味わうと、以前のギリギリギチギチの感覚は不自由過ぎて不安定過ぎて戻りたくありません。
なので全ての音を自由な声帯で歌えるように、常に意識をしつつ、過去の悪い歌い癖をなくすために繰り返し身体に新しい自由な感覚を覚え込ませました。
そうしていてもすぐには全ての音を自由に歌えるようにはならず(いまもまだ全部統一はできてません)、時には昔の歌い方で惰性で歌って不自由、なんてこともしょっちゅうでした。
一度いい声が出せると、このままいける!と突っ走ってしまい、深く考えずに声を出して昔の歌い癖に戻って終わりがち。
今は頭も身体も感覚を変えないといけない時期だから、常に最大限意識をし続ける、ということを心がけていました。
そう思っていてもいつの間にか昔の歌い癖が…ということももちろん何度も何度も何度もあり、そういう時はじわじわ昔の歌い癖に戻っているため、何が悪いのか分からずドツボにはまることもよくありました。
そういう時はもちろん、喋るまま言ってないのが原因なのですが、自分の中でまだまだ甘えがあって「この感じでも歌えるだろう」と、喋るままの場所や言い方とは少しズレたところで言っているんですよね。
要は喋るままで言ってるフリをして、ズルして楽して歌おうとしてるって事です。
(こんなズルしても自分が困るだけだし、むしろ不自由になって楽になんてなってないのに)
なのでこの頃には
上手くいかない
↓
繰り返す
↓
やっぱり上手く行かない
↓
絶望
↓
面倒でももう一度基本に戻ろうとやりなおす
↓
喋るままでできてなんとかなる
を何度も繰り返し、そこでドツボにはまって「頭と身体がズルしてるな」と思った時には、基本に立ち返って、
- 普通に喋る(歌う用の喋りでなく)
- そのままのノドの位置でそのままでいる
- そのまま普通に喋り続ける
ということを意識してやり直してました。
ここで特に大事なのは1と2だと思っていて、①は比較的わかりやすいのですが、私の場合②がものすごくズルします(笑)。
悪い歌い癖のせいで、ノドを押すことでノドが後ろに引っ込んでしまい、ノドが解放されずに不自由になる、という現象が起きることが多かったです。
なので喋るままを意識してもダメなときは、面倒でもこの3ステップに立ちかえるようにしました。
この3ステップも意識するようになってくると、自分がいかに喋るままの声帯(位置や自由さ)で歌っておらず、わざわざ歌いにくいポジションでわざわざノドを固めて歌っていたんだな、と気付かされます。
車で例えるなら、ブレーキを踏みながら(邪魔しながら)アクセルを踏んで(声を出している)走ろうとしているようなもの。
こんなことしてたらスピードが出ないのは当たり前だし、走り(声)も不安定になって危ないし、エンジン(ノドや身体)に負担をかけていることは明らかですよね…。
恩師が私によく言っていた「なんでわざわざ難しい歌い方でやるの?」の言葉は、ここでも私の身に染み続けます。
自分がいかに喋っていなかったかを思い知る
そしてこれらを意識して練習を続けて本番1週間前。
なんとなく声帯を自由に歌わせるという感覚がわかってきました。(全てでできてる訳ではないけど)
それを繰り返しすうちに、その段階の私なりに実感したことがあります。
それは、
- 喋るままで歌う、の本当の意味
- それまでは喋っているふりをして、実際はノドで押したりノドに力を入れて支えたりしていた
- 本当は全てを「ちゃんと」喋るままでいい
- ここて言う「ちゃんと」とはノドで支えたり固めたりするのではなく、普段喋る時と同じに前のポジション、開放感、脱力感のままでちゃんと発音して、声帯に自由に歌わせるということ
- それまでは喋ることではなく、いかに声を前に出すか、はっきり聞こえるように言うか、などの他のことを優先していて、それにとらわれていた。あとメロディの音程にもとらわれていて、ノドだけでそれを作ろうと押していて、喋る以外のことに振りまわされていた
- でも喋る言い方だけで思い切り言えば、正しいポジションと正しいノドでいられる(この「思い切り言う」は力で押すのではなく、普通に喋るだけにするために開き直って、それ以外の要素を排除する、という感じ。覚悟を決めてそれだけで言う!)
- 普通にそのテンションで喋るのって自分にとって一番自然な言い方なのに、その言い方で言わせてなかったんだから、そりゃ歌いづらいしノドも固まったり重くなるよね
という事。
一つ気づくとポンポンポンといろいろ芋づる式にわかることもあるようで、この時は短期間で一気にこれらの事が腑に落ちて、あわててこれらをメモしました。
これらを自分の頭と身体で実感し、とにかく喋るのと同じに最大限近づける!ということを引き続き意識して本番に向かっていきました。
言いたい言い方なんて全くしてなかったことを痛感
すると、さらに変なストッパーがまた一つ外れて、
「あれ?喋るままで自由に歌えるはずなのに、わたし今まで歌いたいように歌ってなかったんじゃない?!」
とふと気づいたのです。
この文章を最初から読んでくださっている根気強い方ならすでに大きな矛盾があることに気づかれていたと思いますが、
私は「喋るままで歌える!」という事をかなり前から頭ではわかっていたにも関わらず、昔からの悪い思い込みや歌い癖に振り回されて「喋りたいように歌う」ではなく、「歌えそうな声で歌う」ということだけをしてきたのです。
だって、ノドが不自由だったから。
不自由だったから、喋るままで何で言えない時思っていたからなんとか歌えそうな他のやり方でとりあえず声出してただけ。
今でこそ「喋るままだけでやってないから不自由だったんだよ!」と自分に大きくツッコミを入れられますが、一昔前の私は本気でこのことをわかっていませんでした。
歌う声とは、それっぽく作るもので、本当の意味で喋るままでは歌える訳ないと思っていたんですね。
(恩師が言ってくれた言葉も、ものの例えだと思ってました)
なので、私は長年、
喋るままでは歌わない
↓
歌いにくいから声を作らないと歌にならない
↓
声を作らないと歌えないと思い込む
↓
喋るままでは歌えないと思う
の負のループをえんえんと繰り返していたのです。
人間の思い込みと習性って本当にすごい…。
ですが、恩師の教えのおかげで遅ればせながらこのことに気づけたのはラッキーです。
今まで悪い方向に思い込みと癖づけをして、ナチュラルに不自由な声を出すようになったのなら、
これからは良い方向に思い込みと癖づけをして、ナチュラルに喋るままで自由に歌える自分になればいい!
自然とそうポジティブに思えたんです。
こう書くと「ものすごく努力する人」のように思われるかもしれませんが、努力とかそんなのではなく、ただひたすらその感覚で歌えることが楽しかったんです。
本来面倒くさがりの私にここまでモチベーションを与えてくれたのは、「このまま行けばもっと自由に楽しく歌える」というワクワク感で、
「歌うことは好きだけど、歌うのは大変」という感覚を持ち続けていた私にとって、この自由さと開放感は大きな新しい一歩だったんです。
「普通に喋るだけ」=「自由に言うための方法」と気づく
そのワクワク感に引っ張られつつ本番に向けて練習を続けていると、また新しい気づきが。
それは、
普通に喋るだけで言ってれば、自由に言えるポジションにいられて、声帯も自由でいられる
という事。
さんざん同じことを書いてきていますが、このタイミングでようやく腑に落ちました。
この時に実感したのは、
恩師が「普通に喋るままだけでいい」と言っていたのは、ベルカントで自由に歌えるポジションと声帯でいさせるためだったんだ!
ということ。
それまでの私は、
前にいないと!
ノドを脱力させないと!
ノドで押しちゃダメ!
息で押さない!
呼吸を深く!
などの枝葉のことばかり気にしていて、「これらのことができたら喋るままで言える」と思っていたんです。
上手く伝わるといいのですが、恩師は「喋るままで言えはいい」とそれだけをやるように言ってくれていたのに、私は喋るだけでは歌えないと思い込んで、「○○ができたら喋るままで歌える」と思っていました。
でもそれは完全に本末転倒で、恩師の言う通り喋るままだけで言ってれば自由自在に歌えるのに、私は「喋るままでやるためにまず他のことをクリアしないと」と思っていたため、結果喋るまま以外のことばかりやろうとしていた、ということ。
これに気づいたとき、「私はなんて遠回りしてたんだ!」と愕然としましたね。
恩師が何度もわかりやすく言ってくれていたにも関わらず、私の勝手な思い込みでわざわざ歌えない方向に進んでいたなんて…(涙)。
そんな私を見捨てず、根気強く何度も何度も軌道修正を試みてくれた恩師には心からの感謝しかありません。
恩師から離れてからも、恩師の言葉だけを頼りに一人でやってきましたが、ようやく恩師の言葉の本当の意味がわかった気がしました(それでもまだ勝手な解釈をしているかもしれないけど)。
だんだん声帯が自由になってきた
このことに気づいた私は、
- まず、言いたいように言う!
- 言いたい言い方だけで言えるから、ワガママに言いたい言い方だけで言っていい!
- 言いたい言い方だけで全てを支配する!
- 言いたい言い方以外のことは振り切って、思い切り言いたい言い方だけで言う!
という考え方を取り入れて練習を始めました。
すると、以前はほとんど感じたことがなかった、声の幅というか、声を自由に動かせるスキマみたいなものができてきたんです。
これは感覚的なものなので分かりづらいかもしれませんが、以前は声帯やノド、口周りが全く動かせずギチギチになって力ずくでやっていたのが、
喋るだけて思い切り言うことで、喋るままの前の自由なポジションのままでいられて、ノドから声までの間と声の周囲に自由に動ける空間ができ、声だけが前ででふわふわ宙に浮いているような感じになったんです。
(ここでノドで押そうとすると声は逆に後ろに引っ込んで不自由になってしまうので、普通に喋るだけの範囲で喋るだけにとどめます)
これでやっていれば、「喋る時と同じ感覚で言えるじゃん!」というのが本能的にわかるので、喋る時と同じ喋りのライン上で言うだけでやるのが一番楽で滑らかに言える、という事もわかりました。
喋るままで言うためには喋る言い方にひたすら近づければいい、と思っていた私でしたが、結果的に分かったのは
ふだん普通に喋れてるんだから、そのまま言うだけで普通に喋るのと同じように自由に歌える
ということで、そしてそれをやるのが一番簡単でシンプルな方法だということでした。
だから先生はあんなに何度も言ってくれてたんですね…。
先生の言葉をそのまま素直に受け取っていたらもっと早く上手くなっていただろうに…(涙)。
だから、「どうやったら喋るままで言えるか」ではなく、「喋るままで歌いたいなら、ただ喋るままで言うだけ!」ということだったんですねー。
本番前に感じた、小さな違和感
この事に気づけたのが本番数日前。
「次の本番では一味違うワタシ…」なんて思いながら練習を続けていました。
とにかくひたすら、喋るままでただ言うだけでいい。
この事にようやく気づけた私は、その感覚をひたすら頭と身体に叩き込むことを繰り返していました。
頭ではわかったけど、身体やノドは前の歌い癖が残っている。
それをなんとか新しい感覚で上書きして、0.1ミリでも自由な方向に進みたいと必死でした。
そんな地道な繰り返しが功を奏したのか、歌いにくかったフレーズもスルスルと歌えるようになっていき、以前は一曲を通すだけでもしんどかったのが多少は楽になり、ますます歌うことが楽しく感じられるようになってきました。
以前に感じていた変な身体の負担も減り、長時間歌っても心地よい疲労が残る程度になってきたんです。
(変なことしてた頃は身体にも不自然な使い方をさせていたようで、歌ったあとは変な疲れ方をしてました)
全部完璧とは言えないけどとりあえずは歌える。
歌ってて楽しい。
しばらく味わったことのないこんな感覚が嬉しくて、目の前に迫ってきた本番への恐怖はいつもよりは少なかったです。
ですが、この時、「ある程度思う通りに歌えるようにはなったけど、この言い方で客席にちゃんと届くかな?」という一抹の不安もありました。
私は普段練習の際にスタジオを借りていて、そこは3〜4帖のコンパクトさなので、広いホールでどう響くかが分からなかったんです。
しかも本番で歌う曲は歌曲で、低めの音から始まるため、無理に押さないように普通に目の前の人に話すぐらいの感覚で喋っていました。
この言い方で、ちゃんと聞こえるかな?
本当はもっとワガママに、言いたい言い方で言うだけでいいんじゃないか?
私はどこかでまだまだ遠慮しているのかもしれない。
そんな風に思ってはいましたが、その時の私はその時点でたどりついた言い方しかできません。
とりあえず失敗はしない程度には出来上がっていたので、今の私のままでいく!と本番を迎えたのです。
本番の舞台で目標とする声に出会えた
そして本番当日。
今回は今までよりも楽しく歌えそうだと内心ドキドキとワクワクしながらホールへ向かいました。
舞台衣装に着替えて自分の出番が来るのを舞台袖で待ち、私の前の方の番になりました。
その方はソプラノで、私は初めてご一緒する方でしたが、この方の歌が素晴らしかったんです!
とても美しく豊かに響く声で、その方が歌い出した瞬間、一瞬で「私の歌い方は違う!」と感じるほどでした。
そして、「この人みたいに響く声で歌いたい!」と強く思ったんです。
私は普段は一人で練習しているので、自分の声を自分で聞いて修正するしかできません。
なので他の人との比較もできないし、誰かに指摘されることもないので、自分の声がどう響いているのかを実感しづらいんです。
それが、この時出番直前でその人の声を聴いた瞬間に、「響く美しい声ってこうだ!私が目指したい声ってこれだった!」とわかったんです。
すごく美しく素晴らしい歌を歌う方の後に歌うことになったのには多少のミジメさはありましたが、この順番でなければ近くてこの方の声を聴くこともなく、しばらくの間、自分なりの響く理想の声に気づくことはできなかったでしょう。
なのでこの順番でラッキーだったと今では思っています。
そして私の出番に。
いざ舞台で歌ってみると、やはり自分の声がホールに通っていない感覚がありました。
自由な声を目標にして練習したかいはあり、スムーズに歌える感覚はありましたが、声のスケールが小さいように思いました。
前の方は身体全体で響いていて、ホールのすみまで伝わっていたので、全然違う感覚でした。
今回の本番に向けて喋るままで言える、という事に気づくことはできましたが、ホールの奥の人にもちゃんと伝えられるような言い方をしてなかったのが大きな失敗でした。
つまり、言いたい言い方の通りにある程度は歌えていたのですが、そもそもの伝え方や言いたい言い方が違ったために、響くポジションにいられなかったのだと思います。
あと、低い音の部分はもともと苦手意識があってノドで押す度合いが強かったため、普通に喋るままの習慣がまだついていなかったというのも良くなかったですね。
ですが、喋るままで言える、言いたい言い方で言うのが一番早い、一番楽で自由、という事に気づけたのは大きかったです。
とは言え、もっと早く言い方に気付けていたら…!という悔しさもあるのですが。
これからは他の方の声も参考にして自分の声と照らし合わせつつ、伝わる言い方の感覚をより磨いていきたいです。
そして、もっともっと感じるままにワガママに、本当に伝えたい言い方だけで言う!ということをつきつめていきたいです。
ちゃんとホールのすみまで聞こえる、きちんと伝わる響く声、そして言いたい言い方だけで思い切りワガママに言うだけ!というのが当面の目標ですが、これができるようになるまでにまた何度も同じ道を行ったり来たり、脱線しては気づいて、の繰り返しになるのかもしれません。
また新たな道が見えてきた時に更新しに来ようと思います。
本当に普通に喋るだけ、そしてそれを拡大させるのは身体の役割(2023年9月から2024年1月の移り変わり)
2024年1月に本番が終わり、一区切りついたので更新しています。
このパートは23年9月から24年1月までに気づいたことを書いていきます。
見出しにも書いたように、この数か月やってきて気づいたのは、
「本当に普通に喋るだけで良く、それを皆さんに届く歌に拡大させるのは身体の役割」
ということ。
前回の更新部分(このパートの直前部分)の最後に書いた、「もっともっとホールの奥の人に届くように伝える!」ということを目指してここ数か月やっていたのですが、
もっと響かせようという気持ちが強すぎて、逆にそれがノドや息で押して効率悪い歌い方になってしまいそうだったので、いったんそれを強く意識するのはやめることにしました。
やはりどこまでも重要なのは「喋るのと同じ言い方で言う」ということなので、引き続きその言い方に1ミリでも近づく(その純度を上げていく)という作業を続けていきました。
ひたすらその作業を続けていると、
- 歌おうとするときは喋るのと違って歌い始めに余計なアクションをしている
- 歌おうとするときは喋るのと違って口やノド周りに力がはいっている
- 歌おうとするときは喋るのと違ってポジションを引いてこもった場所で歌っている
- 歌おうとするときは喋るのと違って浮かせた場所で歌っている(高い音を歌うため?)
という、余計な癖があることがわかってきました。
ここまででさんざん余計な癖がとれてきた、と思っていたのですが、かつての歌い癖は根深いようで掘っても掘ってもまだ歌い癖が残っていました…。
おそらくこの前の期間の本番で自分の声がホールに通っていない感覚があったのは、これらの歌い癖のせいで声がちゃんと響いていなかったからだろうなと分析。
そもそもの喋り方が違ってた
しかもしかも、もう一つ重要なことに気づいたのですが、ここまでで「歌う時は喋るのと同じに言う」とさんざん言っていたし、実践してきた私ですが、実は
その基準になる喋り方が間違っていた
のではないかと!!!
これ以前も「喋るまま歌う」ということを大切にして、喋る声を基準にして歌の練習をしてきましたが、
基準にしていた喋り方が「歌う前提の喋り方」
だったんです!
そもそも「喋る声で歌う」ことがなぜ重要なのかと言うと、人は喋っている時が一番自由に声帯が動くようになっているから、という考えから来ています(別のメソッドの場合は違う考えになるかもしれませんが)。
普通に喋っている時は
「声がちゃんと出るかな」
「高い音にスムーズに移行できるかな」
「ちゃんと声が出るように準備しないと」
などといった事は考えなくても、一瞬で言いたいように声を出して喋ったり高音で悲鳴をあげたりすることができますよね。
ですがこれらの自由な声は普段通りナチュラルに喋っている時に使えるもので、声の心配をしたり出す準備をしたり歌う声を作ったりしてしまうと、逆に自由な声にならなくなります。
なので、「喋るまま歌う」というのは確かに重要で喋り声を基準にすることは良いことのはずですが、自由に歌いたいのであれば、「歌う前提で作った喋り方」を基準にするのではなく、あくまでも「普通に喋っている喋り方」を基準にしなければ自由な声にはなりません。
「歌う前提=歌う準備をしている」ということになりますから、普通に喋っている喋り方からは遠ざかります。
つまり、「歌う前提の喋り方」を基準にすると、いつまでも自由な声にはなりきれないということになるんですね。
ここまで来てようやくこのことに気づいた私は、「その音程で普通に喋る喋り方」を基準に切り替えました。
すると、声やノド周辺を縛っていた何かから解放された感覚になり、かかっていたブレーキが減った感じがしたんです。
ここでも再度、「本当に普通に喋る声でいいんだ!」と目からウロコがバッサバッサと落ちました。
響きを作るのはノドではなく身体、身体が拡声器
そしてその感覚になってみてようやくわかりました。
それまでの私は「もともとの声を大きく響かせようとしていた」ということに。
「大きな声を出さなくていい」と恩師にさんざん言われていて、頭では分かっていたつもりでしたが、結局は何もわかっていませんでした。
歌う前提の喋り方は声を大きくして皆さんに聴かせようとする喋り方なので、普通に喋る喋り方からかけ離れ、ノドや息で押す力が多少なりとも加わります。
ですが本当に普通に喋るのと同じように歌うようにしてみると、逆に口やノド周辺に力を入れることができなくなるので、身体に声帯が楽に動くように助けてもらいつつ響かせるように働いてもらうしかなくなります。
ギターやバイオリンなどの弦楽器に例えると、音を作るのは弦部分だけでコンパクトに行うけど、それを拡大して響かせるのは楽器のボディ部分の役目なんですよね。
それと同じで、口やノド周辺や声帯は普通の喋り方で自由に喋れるようにして音程を作るだけで、声を拡大して響かせて周囲に聴かせるのは身体の役割なんだと。
だから声帯が自由に動くようにサポートするために、お腹の支えが必要だと。
(喋るのと全く同じに歌うと言っても結局は喋るのではなく歌いたいからやっている訳で、普通に喋るまま言うだけでは歌声にはならないのでその部分を身体にサポートしてもらう必要があるから)
長年声楽を勉強してきて、ようやく多くの方が仰っている「身体やお腹で支える」という意味がわかってきたのです!
ここまで来ないとわからない私って…、とも思いますが、気づけて良かった…。
「身体やお腹の支えが重要」というのは声楽でよく聞く話ですが、私はここに来るまでほとんどその意味がわかっていませんでした。
その通りやろうとしても全然改善しなかったので。
でも今ならわかる。
体やお腹で支えようとしても歌が改善しなかったのは、ノドや口に余計な力が入りまくっていたから!!!
ノドや口が脱力したままで自由に歌うために身体やお腹の支えが必要なのに、そもそもノドや口に余計な力が入っていたら自由にはなれるはずはないので、身体で支えても全く意味がありません(むしろ全身ガッチガチ)。
軟口蓋を高くする必要性がようやくわかった
ここにようやく気づいた私は、
- 身体という拡声器を使っている感覚になる
- 口やノドでは普通の声のまま喋る
- 普通の声のまま喋れない音程や音型の部分では口やノドに力が入らないように身体に支えてもらう
ということを意識するようになりました。
するとすると、以前はちゃんと言えなかった細かい音とか、歌いにくかった箇所が自然に歌えるようになってきたんです!!
これを繰り返しているうちにまたなんとなく押すようになってきたので、初心にかえって明るい発音を意識してみると、これまた歌いやすい!
恩師には「明るい発音で言って!」と何回も注意されていたのですが、私はこの明るく発音するのが苦手でした。
明るい発音をするとなんだか不安定になるし、支えがない感じでフラフラしてしまうことが多かったので、なんとなく口を半分閉めて少し色をつけた歌い方をしていたんです。
でもこれも今ならわかる。
以前は余計なことばかりして押していたからで、押すときは前向きの力が加わります。
逆に明るい発音は口をタテにあけて開放するので、余計な前向きの力があるまま明るい発音をするとその場所で開放していられず、グラグラして不安定になってしまっていたんです。
でも普通の喋り方でノドや口で押す度合いが減ってきたいま、明るい発音をすることでより声帯周辺が開放されて、さらに声帯が自由に動けるようになりました!
そしてこれも今さらなのですが、これが多くの方が仰っている
軟口蓋を高くする(鼻の後ろをあける)
ということなんだ!!!!とわかりました…。
これもよく言われていることですが、以前の私はこれやっても全然ダメだったんですよ。
むしろ余計な力が加わって全然歌えなかった。(なので恩師は私にはこれをやらせることはなかったです)
原因は先ほどと同じで、余計なことして押しまくっていたから、余計な前向きの方向と軟口蓋を高くする上向きの方向が相容れずにスムーズにできなかったのでしょう。
でもね、普通に喋るようにして口とノド周辺の力を抜いて明るく発音したら、自然と軟口蓋が高くなったんですよ!
最初は「なになにこの感覚!?」と戸惑いましたが、軟口蓋が高くなると声帯周辺が開放されるせいか、より喋りやすくなるんですね!(←みんな知ってる)
ちなみに誤解して欲しくないのですが、「明るく発音」というと不自然に明るい声を作りたくなりますが、これはあくまでも普通に喋っている範囲内での明るい発音、ということなのでご注意ください。
少し自由になってきた
そしてこのことに気づいてしばらくはこの意識でやっていたのですが、なんせ前に押す習慣が長いことあったので、「口とノドは脱力、軟口蓋を高く」と思っているだけではいつの間にか以前の押す喋り方に戻ってしまいます。
そこで色々試して落ち着いたのが「口先だけで明るく喋る」ということ!
口先だけで喋るってなんだか良くない事のように感じられますが、今の私にはちょうどいい感覚。
口先だけで喋るようにすると、
- 口の中やノドに力が入りにくい
- ポジションが前にいられる
- 大きな声を作ろうと頑張れない
という効果があり、自由に喋れて、身体に響かせてもらう大元の声を作りやすくなります。
この練習をした後に本番がありアリアを歌ったのですが、この感覚は自分的にはわかりやすくまずまずの出来でした。
私はずっと自分の歌の不安定さやがんじがらめな感じがとても嫌で、スッと一曲を歌えないことが強いコンプレックスだったのですが、その原因がようやく分かった気がしています。
もちろんまだまだ外していくべき余計な習慣や癖があると思いますが、進むべき方向はこっちで良さそうだという目処が付いたのがとても嬉しいですね。
しかし、本当に恩師が言っていた言葉は全て真実で的を射ていて、ひれ伏すしかありません。
身体に任せるということが出来ていなかった頃は、低音や高音は押しまくっていたので、低音と高音部分も身体に働いてもらって自由に歌えるようにさらに新しい習慣だけに塗り替えていきたいなと思っています。
また新しい気づきがあったら更新しますね。
大きく一歩前進!ベルカントの歌い方が本当にわかった気がした気づきを得た(2024年2月から2024年8月の移り変わり)
この部分は2024年8月に書いています。
8月に歌の勉強会があり、そのために軽く準備をしていた段階で、私にとっては大きな大きな気づきを得たのでその感覚と考え方を備忘録目的メインでシェアしたいと思います。
「もっと簡単に歌えるはず」というイメージはかなり前からありました。
なので、歌うときに余計なことをたくさんしているのではと言う自覚もありました。
世の中の歌がうまい人たちは、体や喉について神経質に考えながら歌っているようには見えなかったので、歌いながら気にしていることや、どういう風に歌いたいかと言うところが私とは違うんだろうなと思っていました。
練習していく中で、もっとシンプルにもっとしゃべるだけで、もっと楽に歌えるはずと言う感覚を少しずつ少しずつ追求していくようになりました。
今回の勉強会ではその前に練習する時間があまり多く取れなかったため、チャレンジングなものをやるよりも、知っているけれども、あまり歌ったことがないようなドイツ歌曲などを中心に勉強して準備していました。
ドイツ語は大学でやりましたが、今では発音もあまり詳しくなく大部分を忘れているため、練習時間が少ない分、ドイツ語の他の歌詞をすらすらと言えるように歌詞を見ながらぶつぶつと発音を繰り返すと言うことをやっていました。
このドイツ語の歌詞をとりあえずフラットに、ぶつぶつと、発音にだけ注意して、感情や音程に関しては何も考えず、口先だけで何度も何度も繰り返し読んでいるときに、気づきが降りてきました。
発音することと音程を作ることは別の話だと気づけた
ドイツ語の歌詞は私にとっては不慣れなので、音程や感情などをつける余裕がなかったのですが、それが良かったのかもしれません。
ただ歌詞を繰り返し発音していくとその発音に慣れてきます。
そうして発音に慣れてくるとリズムで言えるようになってきます。
リズムに乗せて発音を言えるようになってくると、この歌詞の部分はこういう音程だということが、なんとなくイメージで頭のなかで浮かんでくるようになってきます。
感覚としては口ではぶつぶつとただ言葉を発音しているだけで、ただそれだけ。
でも頭の中ではリズムと音程が思い浮かべられていて、それが勝手に同時で進行されている。
そういう感覚にで歌詞が発音できるようになっていきました。
それを少し続けていくと、変な喋り方(変に音程を作ろうとしたり、変な言い回しをしようとする)や、色気があるような言い方、つまりただ喋っているだけではなくて、何か作為的に歌おうとしたり、作為的に外側で音程を作ろうとしたりする時には、頭の中で音程が同時進行されずに、音程やメロディーが思い浮かべられずに止まってしまうと言う感覚になりました。
逆に言えば色気を出さずに、ただ普通に喋って、いつもしゃべっているその場所で普通に発音しているだけであれば、発音しているのと同時進行で音程やメロディーが思い浮かべられるようになっていたんです。
このことに気づいて、それまで自分が歌うときにはただ歌詞を発音するだけではなくて、色気を出して力任せにしたり、息を回して発音したり余計なことをしていると言うことに改めて気が付きました。
そして音程やメロディーが頭の中で同時進行で浮かび続けられるように発音しようとする場合、喋り方や音程を作ろうと色気を出さずに自分の普段の喋り方で普通にその普段の喋り方の場所にいるままでしゃべる、発音するしか方法がないと気づいたのです。
それに気づいた瞬間、歌う時も、これと同じように自分が発音するのと声が響いていくのとは、本来は全然違う部分が働いているのではないかと言うふうに自然に思えたのです。
なので、自分がやる事はただ普通に発音するだけ。そして声が響くと言う事は、普通に発音した結果、余計なことをせず邪魔するものがなく芯だけで言えている状態だから、外側に向かって響きやすくなるし、邪魔が少なくなるから歌っているときの苦しさや不自由感も減って、自由に簡単に歌える感覚になって行くはず。
この時はただ歌詞を発音しているときに、この感覚になれた(初めて気づけた)だけでしたが、この時に私はこの感覚であれば、今までよりも明らかに楽に明らかに自由に明らかに響く声で、明らかにより楽しく歌えるようになるはずと言う確信に近い感覚になれたのです。
喋る以外のことをしていたから不安定になっていた
そして、翌日に練習を始めたときに、その感覚に沿ってやってみたところ、大当たり!
自分はただ普通にいつもの場所で地味に発音しているだけ。でもその場所にいる。そしてそこで余計なことをせずにただ普通に言っているだけ。だからこそ、余計な邪魔が入らず、声がちゃんと外側に向かって響いていくし、邪魔がないからこそ歌っていて疲れにくい。
自分で何とかして声帯や身体を使って声を響かせよう、音程を作ろうと思っていた時は、その作為的な部分が邪魔をして必要のないことをやっていたため、すぐに疲れるし、邪魔なことをしているからとても歌いにくいし、いろんなことをしているからポジションが一定の場所にいられなくてフラフラしているから不安定になってしまって、次の音がちゃんと言えるかどうかが恐怖で安心して歌を楽しむと言う感覚はあまりありませんでした。
不安定なままでやっていくと、気持ちも声も不安定で、次の声がちゃんと出るかもわからないので、さらに次の声をちゃんと出そうとして、不安定な場所で作ろうとするから、無理矢理固定して作るしかなく、がんじがらめな状態で声を出すため、さらにポジションが悪化して…と言うふうに悪循環におちいっていました。
でもこの感覚になってみてはじめて翌日に練習をしてみて、この感覚にはまっていったときには、「これなら楽しく歌える。これなら言いたいことが言える。これなら表現できる。これなら数曲連続して歌うこともできる。」と言う感覚になれました。
これまではポジションが不安定すぎるからそれをなんとかしようと身体と喉に負担をかけすぎて、ガチガチになりすぎていたし、身体と喉がすぐに疲れてしまっていたため、こういう感覚で歌えた事はほとんどありませんでした。
自分で全部やろうとしない、がすごく大切
先生が私に言ってくれた事は全て本当でした。
「私はただ普通に喋るだけで何もしなくていい。」
「その曲を知っていて、メロディーを知っているのであれば、音程が勝手に作ってくれるから、私がみずから音程に付き合う必要もない。」
「そして声のことを考えるのではなくて、どういう風に喋りたいか、どういう口調で言いたいかが1番先である。」
「声のことを考える必要がなくて、音楽と歌詞のことだけを考えることが大切。」
これらの事は全て本当でした。
もちろん今この時点で私はまだまだベルカントのスタート地点に立っただけだと言う事はわかっていますが、この感覚だったらこの先も楽しく歌っていけるはずと言う自信がつきました。
「世の中の歌が上手い人たちはこういうふうに歌っていたんだなぁ」とわかった気がしました。
他のジャンルに関しては私は詳しくはないので何とも言えませんが、声楽のベルカント発声と言うことに関して言えば、
- 自分で音程を作らない
- 音程に付き合わない
- 声で感情を表現しようとしない
- 良い声を作ろうとしない
- 普段の自分の喋り方ではない喋り方で言わない
- 自分が普通に無理なく入れる言い方
- そしてその言い方でしゃべれる範疇の場所ポジションのままでとにかく言い続ける
こういう言い方をしていれば声帯に負担がかかりにくいので、声帯は自由に動いてくれて、作りたい音程を勝手に自動で作ってくれて、それに連動して体も勝手に働いてくれます。
私はこれまで、
- 音程は自分で作らなければいけない
- 立派な声に聞かせるために息を混ぜる
- 大きな声を出すために息で押す
- 自分で大きい声を作らないとといけない
- 発音するときは声を出すときに息を使わないといけない
こういう風に思い込んでいたので、この自分の発音と響き(必要な息含む)が、それぞれ違うところで働いてくれる(作業してくれる)と言う感覚や考え方に全く全くほんの少しも、1ミリも、至っていませんでした。
ですが、ようやく遅まきながらこの感覚にたどり着くことができたので、自分の声のレパートリー内であれば、どんな曲でも楽しく歌える、そんな気がしています。
誤解なきようにお伝えしておきたいのは、
「普通にいつもの喋り方で喋るだけで良い」と言うのは、それだけでベルカントの発声ができると言うわけではありません。
それをやった結果として、
- 必要な息が自然に使われて
- 声帯が勝手に必要な分だけ動いて
- 体も勝手に必要な筋肉が動いて
- 楽に響く声を作って響かせてくれる
と言うことです。
ただ、普通にしゃべること以外の部分は、普通にしゃべることで声帯の邪魔をしないようにしていれば、脳みそと声帯と体が連動して全てうまく音程やメロディーを作ってくれて、言いたいように歌うことができます。
ただし、「普通に普通の範疇でしゃべるだけ」「普通にしゃべるポジションの場所にいてただそれをやり続けるだけ」ということができなければ、その時点で余計な邪魔が入っていると言うことになりますから、脳みそと声帯と体が自動で連動して音程やメロディーを作ってくれると言う事はなくなりますし、余計な邪魔が入っていれば力が入ってしまい、響きやすい声も作れなくなるので、不自由な感覚に陥ってしまいます。
ベルカントでは華やかな作業はない(結果的に華やかな響きになるだけ)
なので、この感覚になって歌ってみて思うのが、「歌うことってすごく地味な作業なんだ」と言うことです。
最初からこれに慣れている人であればそんなふうに思わないのかもしれませんが、私は「自分が音程を作らないと」と言うところから始まってしまっていたので、特に高音や低音を出したりするときには、思いっきり構えて力を入れて、歌いごたえを求めていました。
感情を込めたいメロディーにはその感情を表す方法として力で押したり息で押したりと言うことも、それが表現だと思ってやっていました。
ですが、この普通に言うだけというところにたどり着いた今、自由に楽に歌うと言う事は、ただ1点で自分の普段の言い方通りに喋り続けるだけと言うことなので、華々しさや歌いごたえ、大きく振りかぶるといったような事前準備がないので、本当に地味な作業を淡々と続けていくだけなんだなと感じています。
ですがだからこそ、必要以上に声帯や体に負担をかけないで済み、長いアリアや難しい高音やアジリタなどを落ち着いて言い続けることができるし、何曲も続けて歌うことができるし、ちゃんと人に聞こえるような響きで歌うことができるし、普段の自分の喋り方だけでやっているので自分らしさが溢れる歌を歌うことができ、表現と言うことをようやく始められる、と感じています。
小手先で瞬間瞬間でとりあえず良く聞こえそうな声を無理やり作る必要がなく、落ち着いて自分の言い方で言い続けられるので、これが自分の歌、これが自分の声だと人に自信をもって聴いてもらえる、という安心感もあります。
以前は歌をやっていると人に言って、「聴いてみたいです!」と言われると嬉しい反面、「こんな不安定な歌で浅いペラペラな声、聞かせてもがっかりされるだろうな」と本当に思ってましたからね。
あと、歌い終わった後に喉が必要以上に枯れる、喉まわりが重い感じや、しゃべりにくい感じというのもかなり減りました。
ベルカントの道にようやく立てた気がする
今回のことは私基準で見れば、かなり大きく一歩前進できた出来事でした。
昔から歌うことは好きでしたし、歌ってると楽しいとは感じていました。
ですが、今回お伝えしたように以前は全てを自分でやろうとしすぎて、不自由さの極みみたいな歌い方をしていたので楽しさは7割ほど減っていたと思います。
以前はその3割を楽しんでいましたが、今回の気づきで体感的には楽しさが3割から7割くらいに爆増したため(笑)、かなり気分が違います!
もちろんまだまだ課題はあるのですが、「この道の上でさらにスムーズにどうやるか」という課題なので、進むべき道が見えた今となっては不安はなく、むしろ「ここからさらにスムーズになるなんて、早く進んでみたい!」というワクワクさしかないです!
それもこれも、進むべき道がわかったからこうなれてるわけで、何をすればこの道にたどりつけるかわからなかった以前は、「みんなが進んでいるであろう楽しく歌える道がどこかにあるはずだけど、それはどこにあるんだろう…」と思いながら沼地をさまよい歩いて疲れながら歌っていました。
ですが、進むべき道がわかった今は、
- 声が出ないかもしれない心配がない
- 難しそうなフレーズも「どうすれば歌えるのか?」という疑問がかなり減った(喋るまま歌うだけでいいから)
- 響きで歌うと声と身体に負担がかからないため、言いたいテンポやリズムそのままで無理なく歌える
- 負担が少ないため歌ってて疲れにくく、長い曲も普通に歌えるし数曲連続で歌うこともできる
- 自分が言いたいように歌える(表現できる)
- 声の心配は最小限になるので音楽を楽しんで音楽の一部になって歌えるようになった(声以外のことも考えられる)
- 自分だったらどう言うだろう、という観点で曲を見られるので新しくいろんな曲を歌いたくなってくる
など、良いことしかありません!
もちろん、もっともっと素敵に歌える余地はありまくりで、外から見たら伸びしろ99%みたいな状況なのかもしれません。
ですが、歌が上手く歌えることも大事ですが、私はそれよりも求めていたのは「自分の言いたいように、楽しく、自由に歌える」ということでした。
歌うことは好きでしたが、不自由に歌っていると苦しくて、楽しさがどっかいってしまって…自分は歌うべきではないのでは、という気持ちが強くなってしまいます。
音楽が好きで歌が好きなはずなのに。
不自由な時は自己嫌悪と不安と恐怖の中で歌うことも多く、好きだからこそもっと楽しく歌いたい!
楽しさをもっと感じたい!
と常に思いながら歌ってきました。
それがいま、ようやく叶ったと言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、私にとっては長年願ってきた一番の願いが叶ったと言ってもいい、と思っています。
歌い方に悩んでいる方にいまの私が伝えたいこと
もしこの文章を読んでいる方で、声楽の歌い方に悩んでいる方がいるとしたら、その方達にお伝えしたいです。
自分で全部やろうとしないでください。
自分で全部作ろうとしないでください。
自分で全部頑張らなくても、普通に喋れますよね?それと同じことです。
絶対に、もっと楽に歌えます。
絶対に、もっと簡単に歌えます。
絶対に、もっと自由自在に歌えます。
絶対に、もっと楽しく歌えます。
この言葉を聞くだけで何になる?と思われるかもしれませんが、いまの苦しい歌い方を作っているのは自分です。
だから、楽な歌い方も自分で選べます。
楽な歌い方に進むためにまずできることは、「もっと楽に歌えるんじゃないか?」といまの歌い方を疑うこと。
身体も声帯も負担がかからないやり方を求めていますから、「もっと楽に歌えるはず」と脳みそが少しでも思えたら喜んでそっちにシフトチェンジします。
もっと楽に、もっと簡単に。
それを追求しつづけてください。
私の言葉が信用できないなら、世界的な大歌手をみてください。
みなさん自分よりはるかに楽そうに、簡単そうに歌ってますよね?
それが答えです。
悩んでいる方は、とりあえず「もっと楽に、もっと簡単に歌えるはず」と常に考えるようにして、そっち方向に進むようにしてください。
ごちゃごちゃ考えはじめると沼にハマりますから、迷ったり辛く感じた時も「もっと楽に、もっと簡単な方へ」が進むべき方向です。
私ももっと楽に、もっと簡単に、もっと楽しくを合言葉に、さらに進んでいこうと思います。